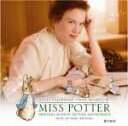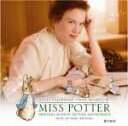
童話,ピーター・ラビットの生みの親,ビアトリクス・ポター(Helen Beatrix Potter, 1866〜1943)の半生をしっとりと描いた佳作。絵のように美しい湖水地方の風景がすばらしく,ピーター・ラビットのファンならばその豊かな自然に心を奪われるはずだ。同時に,女性の自立という言葉がまだ影も形もなかった20世紀初頭のロンドンで絵本作家として自立し,後半生,ナショナル・トラスト運動に参加していくポターの姿は本当に魅力的だ。多くの人に見てほしい映画である。
だが,実は彼女にはこの映画に描かれていない姿がある。後述するように彼女は生物学・細菌学に大革命を起こすことになる「原核生物と真核生物の共生」という現象をもっとも早い時期に確認した一人なのである。この映画では女性が自立して生きていくことが難しい時代に,いかにして一人で自立した人生を彼女が送ったかを描いているが,彼女にとってもっと困難だったのは,英国において女性が科学者として仕事をすることだったのだ(これがもしフランスやドイツだったら彼女は科学者として活動できたはずだ)。ピーター・ラビットも素晴らしいと思うが,ポターが本当に望んだのは実は細菌と真核生物が共生をしながら生きているという事実を認めてもらうことだった。しかし,20世紀初頭の英国は彼女にそれを許さなかった。このことについては,後ほど詳しく書く。
ビアトリクス・ポターは裕福な上流階級に育ったお嬢様だった。両親ともに莫大な財産をその親から受け継ぎ,夏は湖水地方の別荘で暮らす優雅な日々を送っていたが,彼女は幼い頃から絵の才能があり,別荘で見た動物たちを丹念にスケッチし,その精細なスケッチを見て父親(画家になりたかったが,結局親の希望で弁護士になったようだ)は喜んだ。そして,彼女はいつしか,ウサギたちやアヒルたちの冒険物語を作るようになっていった。
当時はヴィクトリア朝の時代であり,英国の上流家庭に生まれた女性は上流階級の男と結婚することが常識であり,結婚しないという選択枝はありえない時代である。当然,年頃になったビアトリクスに母親は次々と縁談を持ち込むが,ビアトリクスはすべて断り続け,いつしか彼女は32歳になっていた。
彼女は自分の描いたウサギたちの物語を本にして出版するという夢を持っていたが,チョッキを着たウサギたちが登場する童話に興味を持つ出版社はなかなか現れない。そしてなんとか出版してくれる会社が見つかるが,その出版社にしても決して売れるとは考えず,素人同然の編集者に担当させる。だが,彼女の絵の真価を見抜いた編集者は彼女の色調を見事に再現した小さな絵本を完成させ,書店の店頭に並ぶが,その小さな絵本は次第に売れていく。そしてポターが新しい絵本を出すたびに人気を呼び,彼女は作家として知られていくようになる。そして,ポター同様に独身を貫く編集者の姉と知り合い,二人は生涯の友となる。
ポターと編集者の二人三脚で本は順調に売れていき,編集者はある日彼女に求婚し,彼女もその申し出を受ける。しかし,身分の違いを理由に両親は頑としてその結婚に反対する。ヴィクトリア朝のイギリスにおいて,貴族の娘が本の編集者という労働者と結婚するなどありえないことだったからだ。しかし,父親は次第に態度を軟化させ,一夏,別荘で両親と一緒に過ごし,その間に彼への愛情が変わらなければ結婚を認めようといってくれる。別荘でも二人の文通は毎日のように続くが,突然の悲劇が二人を襲う。
何とか立ち直った彼女は自宅を出て自活することを決意し,幼い頃夏を過ごした湖水地方の農場が売りに出されていることを知り,それを購入して底で暮らすようになる。そしてそこで暮らしていくうちに,開発業者が売り出されている農家・農場を買い占めては,開発という名目で美しい風景を破壊している現実を知る。そこで,美しい自然を守るために彼女は印税で得た収入をつぎ込み,売りに出されている農場を次々に購入していく。
大体こんな感じの映画だ。万事控えめで声高に主張することはしない。それでいて作り手が伝えたかったであろうことはしっかりと伝わってくる。そういう意味ではいい映画だと思う。ポター役はレニー・ゼルウィガー。お世辞にも美人ではない,ポッチャリ系なのだが,なんともチャーミングである。親の押し付ける「幸せな結婚」を拒否し,一人で生きて行こうともがく姿はとてもリアルだし,編集者に次第に惹かれ,求婚され,嬉しいんだけど戸惑ってしまい,どうしていいかわからない,という場面の彼女は表情はほんとに愛らしく輝いている。
だが,問題がないわけでない。あらゆる描写があまりに淡白すぎる気がするのだ。特に後半の農場に移り住んでからの展開はちょっと急ぎ過ぎたと思う。開発業者との対立もあったろうし,それで関わってくる弁護士との関係も映像だけからはよくわからない。エンドロールで二人が結婚したことが示されるが,これはあまりにも唐突である。さらに,彼女は購入した農場などをすべてナショナルトラストとして国に無償提供したはずだが,そういうエピソードは入れるべきではなかったかと思う。そうでないと,ポターという女性の生涯を綴った映画として完成しないからだ。また,厳格なヴィクトリア朝時代を代表する両親(特に母親)と,解放的なエドワード朝の申し子としてのポターの対立,そしてそれに恋愛話を絡めたら,世代間闘争が寄り鮮明になったような気がする。
それもこれも,原因は90分という時間だ。時代の移り目で作家として自立する女性を描くだけで90分は必要だろう。さらに後半生の自然保護活動まで描くとなったら,どう考えても120分は最低限必要なはずだし,そのくらいの時間をかけなければ,この稀代の女性は描けないのだ。
これだけでもすごい人なのに,作家になる前の彼女は優れた生物学者だったのだ。この映画では「単なる動物好きの少女」のようにしか描かれていないが,実は彼女の真骨頂はここにあったと思う。彼女の生涯を紹介した本にもこのあたりのことはあまり書かれていないようなので,生物学の偉大な先達としてのビアトリクス・ポターに尊敬の念を込めて,まとめておこうと思う。なお,『共生という生き方』を参考にさせていただいたことを断っておく。
ヴィクトリア時代の英国の貴族社会では,娘を学校にやらないことが普通だった。そのため,放置同然に置かれたビアトリクスは自然史博物館を探検することが日課だったという。子供の頃の彼女が好んだのは,自然の様相を細部に至るまで細密に描くことだった。その才能は湖水地方での休暇でさらに研ぎ澄まされ,彼女は一流の水彩画家であると同時に科学的にも正確無比なものとなった。やがて彼女はアマチュアのコケの研究家と知り合いになり植物学に興味を持つようになる。
彼女が研究対象に選んだのは地衣類だった。地衣類とは岩や木の幹を覆っているカサブタのように見える生物だ。とりわけイギリスは,地衣類の種類が豊富で,いわば地衣類の天国だった。
スイスの植物学者シュヴェンデナーは1869年に,地衣類が単一の生物でなく,菌類(原核生物)と藻類(真核生物)が同盟を結んで生まれたものでないか,という新説を発表する。だが,大半の生物学者はシュヴェンデナーの考えを荒唐無稽なものとして受け入れなかった。
ビアトリクスは地衣類,藻類,菌類の微細な構造を顕微鏡で詳細に研究し,地衣類が二種類の全く異なる生物から成り立っていることを確認する。しかし,当時の大英帝国の植物学者はこの「共生仮説」に強く反対し,すべての生物は動物か植物のいずれかだという切に固執していた。しかしビアトリクスは自分の観察が絶対に正しいことを確信していた。彼女の叔父で化学者であるロスコー卿は彼女を信頼し,リンネ協会に論文を提出するようにアドバイスした。しかし,ビアトリクスの論文は,彼女が女性だという理由で締め出される。それどころか,彼女は学会の公開ミーティングに出席することすら許されなかった。
それでもビアトリクスは王立植物園の理事に面会し,彼女の詳細な線画を見せるという約束を取り付ける。これこそ,シュヴェンデナーの地衣類に関する学説を強く支持する鮮明な図だった。だが,この理事はその絵を見ることを拒否する。そして彼女は二度と生物学の世界に戻ることはなく,彼女の貴重な地衣類を描いた水彩画は引き出しの奥深くにしまいこまれた。
そしてビアトリクスは1904年に『ベンジャミン・バニーのおはなし』を出版するが,初期の彼女の絵本に書かれた木や岩は豪奢な地衣類でちりばめられていた。しかし,彼女の死後に印刷された版では地衣類は姿を消している。
ちなみに,彼女の絵が傑出した科学的研究であるとして地衣類図鑑の挿絵に掲載されるが,それは1967年になってからだった。
1997年,ビアトリクスのために開催されたミーティングにおいて,彼女を不当の処遇したとリンネ協会が公式に謝罪している。まさにそれは,リンネ協会がビアトリクスの発表を拒否したときから100年たっていた。
(2008/10/16)