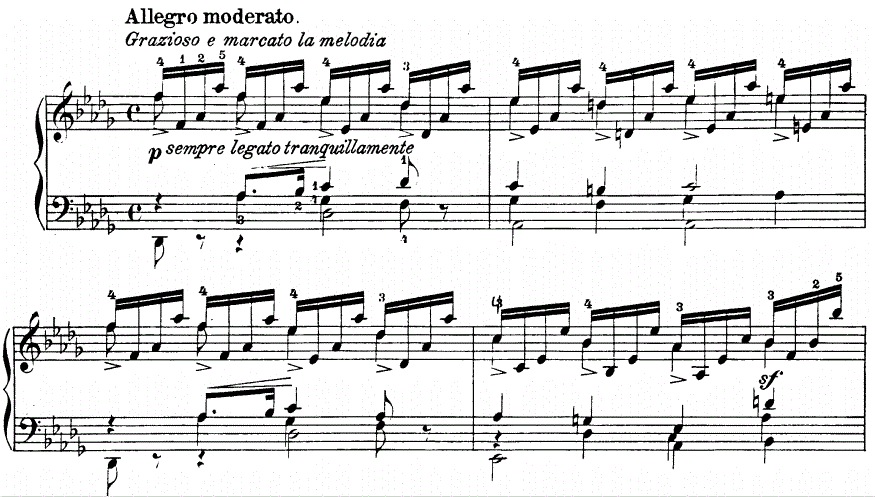
私は基本的に,ピアノが登場する音楽映画に対して評価が甘い。ピアノヲタクだからだ。そしてこの映画は20世紀最高のピアニストの一人,ラフマニノフ(1873年〜1943年)を主人公にしている。だから見る前から期待は高かった。確かにラフマニノフの音楽は効果的に使われているし,映像的にもとても丁寧に作られている作品なのだが,なんだか映画の軸がぼやけている感じであり,残念ながら期待するほどは面白くなかった。
ちなみに,ロシアで作られた映画とあって全編ロシア語で通されているが,ラフマニノフがアメリカに亡命してアメリカで生活するようになってからもロシア語しか登場しないし,アメリカ人同士の会話もロシア語であり,かなり不自然な感じがした。恐らく,ロシアの国内だけで公開する予定だったのだろう。
ロシアの貴族の家庭に生まれたラフマニノフはやがて,ピアノ教師のズヴェレフにその類まれなピアノ演奏の才能を見いだされ,押しも押されぬ天才ピアニストに成長していく。しかし,ロシア革命のために1918年に祖国を脱出し,アメリカに亡命する。並外れた技巧と高い芸術性を持つ彼の演奏はたちまち名声を博し,20世紀最高のピアニストと賞賛され,アメリカ全土を熱狂させていく。
ピアニストとしての名声を得,富を得たが,彼にとっては虚しい日々に過ぎなかった。彼は作曲家として評価されたいと常に願っていたからだ。しかし,ロシアにいた頃,音楽は汲めど尽きせぬ泉のように沸き上がっていたのに,アメリカでは泉は涸れ果ててしまったのだ。母なるロシアの大地への望郷の念にとらわれ続け,苦悩の日々が続くが,そんな彼を妻のナターシャは温かく見守る。
そんなある日,ラフマニノフの元にロシアの春を象徴する花ライラックの花束が届く。その香りに彼は忘れていた過去の出来事を思い出していくが,送り主不明のライラックの花束は演奏会の先々に届けられるようになる。そしてついにラフマニノフは花束の送り主を突き止め,あの名旋律,『パガニーニ狂詩曲』の第18変奏曲が生み出される・・・という映画である。
まず,実在の人物を主人公にした映画であるから,ラフマニノフを演じたエフゲニー・ツィガノフがラフマニノフに似ていて,しかも「ピアノを弾いているように演技できている」ことは必須となる。彼の顔立ちや雰囲気はラフマニノフ(特に若い頃の彼)にそっくりと言ってよく,その点では違和感はほとんどない。また,ピアノを弾くシーンはすべて「弾くまね」のようだが,強く違和感を感じるほどではなく,可もなく不可もない感じである。
問題は,ラフマニノフが身長2メートル近い大男だったことにある。何しろラフマニノフは,「彼がコンサートグランドピアノの前に座ると,ピアノが小さく見えた」と言われるほどの堂々たる体躯の持ち主だったのだ。一方,ツィガノフはナターシャ役の女優とほぼ同じくらいの背丈である。ラフマニノフについて詳しい人ほど,この点には違和感を感じるのではないだろうか。
映画中の音楽の使い方は見事といっていい。例えば,映画の最初の方でラフマニノフが最初のアメリカ公演開で大成功し,全国ツァーが始まるシーン。ここでは「前奏曲嬰ハ短調」(彼の21歳の作品で出世作であるが,音楽的には大したことはない曲。フィギュアスケートの浅田真央ちゃんが使っている曲として有名)の中間部が「壊れたレコードのように」何度も繰り返され,それが機関車の車輪の動きと重なっていく。ラフマニノフが演奏会のたびにこの曲をリクエストされ,弾かされていたことがこのシーンでわかると思う。実際,ラフマニノフの演奏会ではこの曲をアンコールで演奏しないと聴衆は納得しなかったと言われているが,この曲はラフマニノフにとっては若書きの習作に過ぎないのである。これは作曲家としては決して幸福ではなかったと思う。
ちなみに,この映画で何度も登場するライラックの花だが,彼は「ライラック」というタイトルの歌曲を書いていて,その後,彼自身がピアノソロ用にアレンジしている。極めて美しい編曲である。
なお,それ以外に使われていた曲を列記すると次のようになる。
この映画の最大の問題は,時間軸をバラバラにしてエピソードをつなげて行くため,ラフマニノフの生涯や当時の政治情勢(特にロシア革命前後)についてある程度知識がないと,すごくわかりにくい。たとえば冒頭は1920年頃のニューヨークでの最初の演奏会のエピソードで始まり,ついで,ロシア時代のピアノの先生の思い出,「交響曲第1番」の大失敗,ついで1920年のシカゴ,1900年のロシアでの精神療法・・・といった具合である。歴史上の超有名人ならいざ知らず,ラフマニノフ級の人物を主人公に据えるなら,まず最初に,ラフマニノフとは誰か,どういう人物かを説明する必要があるはずだが,何しろこれはロシア映画でああり,「ラフマニノフについてはよく知っている」ロシア人を対象に作った映画である。このあたりは,フランス映画《エディット・ピアフ》に似ているかもしれない。
以下,ラフマニノフについてあまり知らない人のために,この映画を鑑賞するために必要な情報をまとめておく。
音楽家ラフマニノフはピアニスト・ラフマニノフと作曲家ラフマニノフを切り離して論じるべきだろう。
まず,ピアニストとしてのラフマニノフについてだが,ラフマニノフ自身がレコード録音を積極的に行ってくれたおかげで,現在でも多数の演奏を聴くことができるが,いずれも素晴らしい演奏であり,「20世紀最高のピアニスト」という称号に納得するはずだ。彼の演奏のすばらしさは次の二つだと思う。
まず,前者について。前述のようにラフマニノフは身長2メートルの巨人であり,手も大きく指も長かった。12度が楽に掴めたというから,私からすれば想像を超える大きさだ。彼の演奏する様子を見た評論家が「他のピアニストが6度の和音を弾くようにラフマニノフはオクターブの連続を軽々と弾いた」と述べているほどだ。しかもその指は異様に柔軟だった。何しろ,右手の2,3,4,5の指で「ドミソド」の和音が弾け,1の指で5の指の右側の「ミ」の鍵盤を弾けたというから尋常ではない。おまけに,その指が俊敏に力強く動き,あらゆる響きを作り出したのだ。ピアニストとしては,鬼に金棒,最終兵器みたいなものである。
ちなみに,ラフマニノフはマルファン症候群だったという説がある。高身長と手指の長さ,そして関節の異様な柔軟性など,この疾患の特徴を備えているからだ(もちろん,状況証拠でしかないが・・・)。さらに言えば,伝説の魔術的ヴァイオリニストのパガニーニも「高身長,蜘蛛の足のように長く柔軟な指」であったと伝えられていて,ラフマニノフ同様,マルファン症候群だったのではと考える研究者もいる。
「作曲家の視点からの楽曲の再構築」というと,私はラフマニノフの演奏ではショパンの「ピアノソナタ第2番の第3楽章」,いわゆる「葬送行進曲」を思い出す。ここでラフマニノフは,再弱音から次第に音量を増し,主部の最後(中間部に入る直前)で最強音に達する。そして静寂と静謐と安寧の中間部に入り,その後また主部が再現されるが,ここでなんとラフマニノフは轟くような最強音で始めるのだ(楽譜の指定だと弱音である)。そしてその後,音量を徐々に減らし,消えゆくように終わる。楽譜の忠実な再生でなく,新たな「創造」がそこにあり,巨大な演奏である。そしてその大きさが聞く者を圧倒する。このように,ラフマニノフはどんな小曲を演奏しても雄大なものを感じさせる演奏家だった。
ラフマニノフのピアノ曲は彼の身体上の特徴を生かしたものである以上,彼以外の人間が演奏するのは難しくなるのは当然といえるが,しかし実際に弾いてみると「超絶的」というほどは難しくない。ゴドフスキーやソラブジやリゲティの恐ろしいほどの困難さに比べると「常識的な難しさ,頑張ればなんとかなる難しさ」であり,演奏の技術的な難しさで言えばスクリアビンの作品のほうがはるかに難しいと思う(あくまでも私の個人的感想だが)。
また,「12度を掴む手」はピアノの歴史にはしばしば登場する。大きな手でなければ演奏できない難曲といえば,ヘンゼルト(1814〜1889)の「12の練習曲 Op.2」の第2番やタールベルク(1812〜1871)の「12の練習曲 Op.26」の第7番,あるいはタウジッヒ(1841〜1871)の「Moniuszkoの "Halka" による幻想曲」などがある。いずれも指の異様な広がりを必要とする部分があり,通常の日本人ピアニストには「物理的に演奏不可能」ではないかと思う。楽譜の一部を提示するので(楽譜はヘンゼルト,タールベルク,タウジッヒの順),ピアノが弾ける人は是非弾いてみて欲しい。特にヘンゼルトとタールベルクは楽譜で見ると簡単そうに見えるが,見ると弾くでは大違いであることがわかるはずだ(とりわけ,タールベルクの3小節目。中指の音を保持したまま,残りの音を掴めるだろうか。少なくとも私の手では絶対に弾けない)。タウジッヒの曲はもちろんアルペジオで誤魔化すことはできるが,曲想からすると12度の和音として演奏されることを想定していると思う。
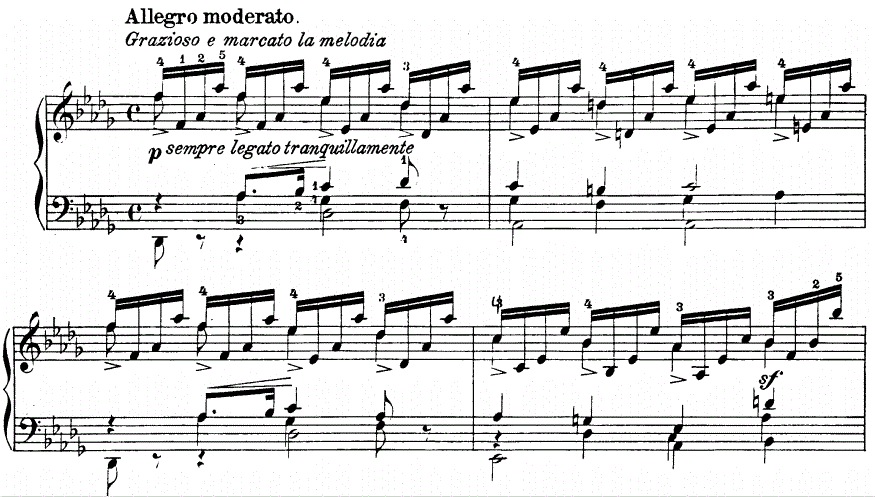
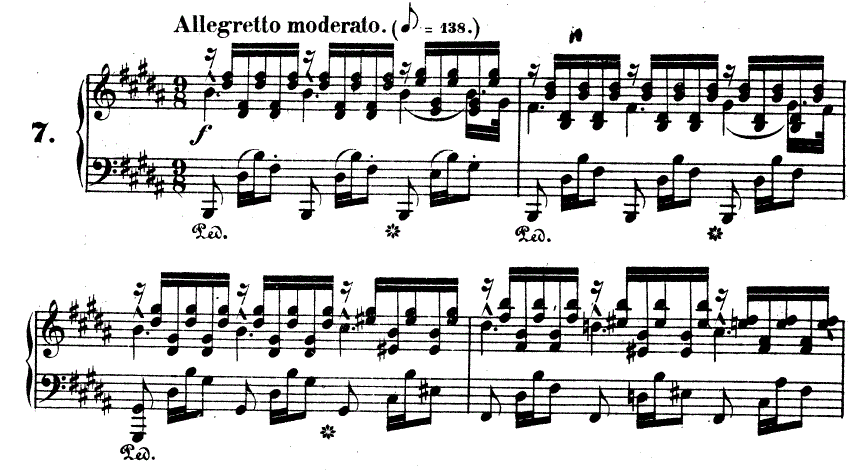
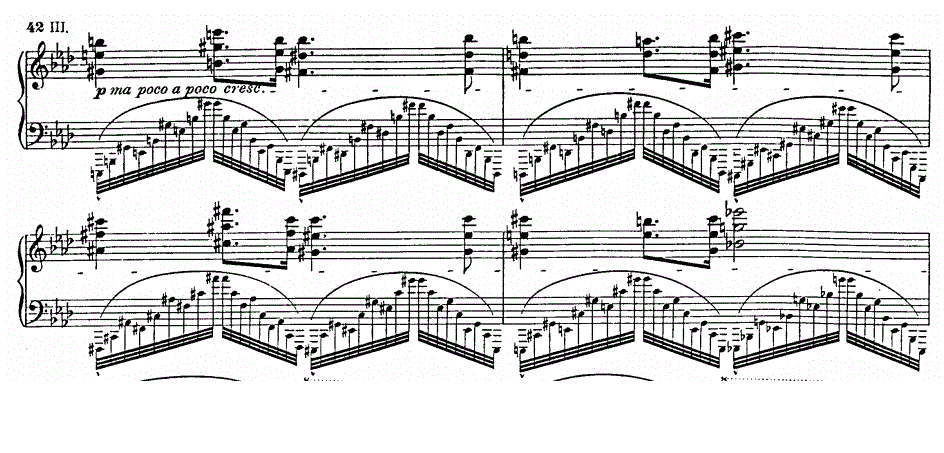
作曲家としてみるとラフマニノフは時代遅れの存在である。例えば「ピアノ協奏曲第2番」が発表された1901年の前後に発表された曲といえば,ラヴェルの「水の戯れ」,シェーンベルクの「清められた夜」等があり,ラヴェルやシェーンベルクが明らかに未来志向であるのに対し,ラフマニノフのコンチェルトは19世紀を向いている。これは彼の辞世の曲となった「交響的舞曲」でも変化はない。同級生のスクリアビンが次々と革新的な表現と可能性を模索していったのと好対照である。
だが,超保守主義だからといって生き残れないわけではない。同時代に発表された「革新的,革命的作品」の大部分が忘れられ,演奏会の曲目から消えていったのに,ラフマニノフの作品はいまだにピアノ演奏会の花形であり続けている。このあたりは,ラフマニノフと同時代人であり,同様に保守的作品を作り続けたプッチーニに似ているかもしれない。
今後も恐らく,プッチーニもラフマニノフも演奏家に愛されていくだろう。世の中にソプラノ歌手とテノール歌手がいる限りプッチーニは生き続けるだろうし,世の中にピアニストがいる限りラフマニノフは愛され続けるはずだ。
(2010/01/12)
