自分が知らないことが書かれている本を読むのは楽しい。そして,自分が自明の理として信じ込んでいたことを根底から覆すようなことが書いてある本に出会うのはもっと楽しい。それが正しいかどうかは二の次で,とにかく常識を否定する発想に出会えることそのものが楽しいのだ。本書はそういう一冊である。
本書はクラシック音楽に精通し,クラシック音楽をよく知っている人が対象だ。これは第一章のタイトル【本当はアフタービートだったクラシック音楽】を見ただけでわかる。クラシック音楽をよく知っている人ほどこのタイトルを見て「アフタービートと言えばジャズやロックのはずだ。クラシックの伝統的リズムを否定したからジャズのアフタービートが新鮮に響いたのだ。著者はこういう音楽の常識を知らないのか?」と猛反発するはずだ。このタイトルはそれほど衝撃的なのだ。どのくらいの衝撃度かというと,「哺乳類は卵を生む」とか「小野妹子は実は女性だった」くらいの衝撃度だと思う(・・・少なくとも私にとってはそうだ)。それくらい「日本のクラシック音楽の常識」からかけ離れているタイトルだと思う。
少なくとも私は,ピアノの先生からも小中学校の音楽の時間でも,「リズムは強・弱・強・弱」と習ってきた。2拍子なら「強・弱」,3拍子なら「強・弱・弱」,4拍子なら「最強・弱・強・弱」だ。これは楽典(音楽理論をまとめた本)の最初の方にも明記されている(例1,例2,例3)。
それこそ「朝起きたらおはようって言いましょうね」とか,「玄関では靴を脱ぎましょう」とか,「赤信号では止まりましょう」と同じくらい基本的常識である。
一方,アフタービート(これは和製英語で,正式にはアップビートというらしい)とは4拍子なら「弱・強・弱・強」というリズムの取り方をいい,前述の「強・弱・強・弱」とは真逆になる。「ジャズやロックの特徴はアフタービートである」というのも音楽の基本的常識だ。
それを本書の著者は「クラシック音楽も実はアフタービートだ」と主張するのだ。これを驚天動地,青天の霹靂と言わずして何と言おうか。
もちろん,本書の著者は思いつきでこんなだいそれた事を主張しているわけではない。ある日突然,ヨーロッパ人のリズムのとり方が気になり,4拍子を口ずさんでもらったら「強・弱・強・弱」ではなく「弱・強・弱・強」に聞こえた,というのがそもそもの発端らしい。そこで彼は「4拍子は強・弱・強・弱」というのは「西洋音楽を導入した時の日本人の誤解」ではないかと考え,まっさらな気持ちでクラシック音楽を聞き直してみたのだ。すると,そこらにアフタービートが溢れていたのだ。実際,本書では20世紀最高のヴァイオリニストのハイフェッツの演奏するバッハを例にあげて説明しているが,ハイフェッツは見事なほどのアフタービートの連続でバッハを演奏していたのである。
この点について,いつもメールのやりとりをしている「福島県在住の生物の先生」からは次のようなメールを頂いている。実は彼は,音楽とピアノの知識はハンパないのである。
バッハのパルティータの例がありましたが,私がまず思い浮かべたのはショパンのワルツ64-2です。まあ,あれはワルツというよりマズルカっぽい作品なので裏拍強調なのは当然といえば当然なのですが,あれなんですが,あれほど演奏家のお国柄が出る作品もないのではと思ったりします。ということで,裏拍にこだわって演奏を比べてみました。
- まず典型的日本人の演奏
「ズン・チャッ・チャ,ズン・チャッ・チャ」と真面目に三拍子やっています。一応,楽譜通り弾いているのですけど,まあ「無音楽」状態。先生のゴルノスターエヴァが密かに苦々しく聴いているのが印象的。- ルービンシュタインならこう弾きます
これがまあスタンダードな演奏かと思われますが,それでもわずかな揺らぎに裏拍への衝動を感じることができます。- 本家のパデレフスキーはこう弾きます
本家と言っても,今こんな演奏をしたら誰も相手しないでしょう。たぶん自分が出した楽譜のバージョンとも違うと思います。でも何か当時の「共通認識」的なものを感じますね。しかし,「西洋音楽論」にも書いてありましたが,それが何かわからない以上は真似はできない。- パハマンはすでに規格外
今の耳で聴くともうなんだかショパンの曲なのかジャズの曲なのかわからなくなりますね。コルトーなどもこの路線。- そして,アート・テイタムが弾くとこうなる
もともと裏拍の曲ですから,いかようにも料理できますね。それにしてもテイタム,ピアノ上手い。豊穣な音楽世界が広がります。
ちなみに,最後のアート・テイタム(1909~1956)は盲目の凄腕天才ジャズピアニストで,あの20世紀最高のピアニストのウラディミール・ホロヴィッツが「テイタムほどうまく弾けたらいいんだけど」と語ったとか,大指揮者のトスカニーニがその演奏に驚嘆したとか,クラシック音楽の巨匠たちからも高く評価されていたことは有名。彼の演奏はのちに採譜されて楽譜として残っているが,右手の超高速パッセージもさることながら,左手の大胆極まりない跳躍の連続を盲目のピアニストが弾いていたという事実に圧倒される。
ちなみに,上記の演奏を私なりに言い換えると,
- 日本人の演奏は「プリンタで打ち出した50音表」。明朝体の文字は読みやすいが,50音表なので内容があるわけではない。
- ルビンシュタインの演奏は楷書。
- パデレフスキーは草書。文字としては認識できるし,書かれている内容はしっかり読み取れる。
- パハマンはかなり崩した草書。だけど,文字としては認識できるし,書かれている内容もしっかり読み取れる。
- テイタムは見慣れない書体で書かれた手書き文字だが,よく見ると草書の基本はしっかりと押さえられていて,書かれている内容もしっかり読み取れる。
ついでに,大作曲家にして名ピアニスト,ラフマニノフによる演奏も紹介しておこう。ここで素晴らしいのは,八分音符が連続する部分で中間部の後に演奏される部分だ。ここでラフマニノフは連続する八分音符の最後の音をわずかに強調し,そこに見事に対旋律を浮かび上がらせているのだ。まさに「作曲家ラフマニノフ」の面目躍如たる名演である。
いずれにしても,「ワルツの3拍子は強弱弱」なんてのは嘘っぱちであることがわかると思う。
「クラシックの基本はアフタービート」という目でクラシック曲の楽譜を見直してみると,実はそこらにアフタービートが見つかる。例えば,ブラームスの名曲『交響曲第4番』の第1楽章第1主題は常に4拍目からフレーズが始まるが,「フレーズの始まりは強く,フレーズの終わりは弱く」という原則からすれば,「4拍目が強く,1拍目が弱い」事になる。つまり,「弱・強・弱・強」でありアフタービートだ(ちなみに楽譜はSingerによるピアノソロ用編曲)。
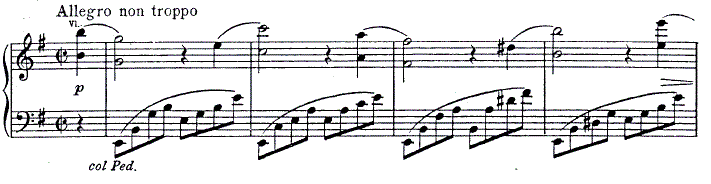
試しに,このブラームスの交響曲のメロディーを「弱強弱強」のアフタービートで歌ってみてほしい。とても自然に歌えるはずだし,アフタービートだからこそメロディーは躍動感に満ちていることに改めて気がつくと思う。しかし,逆に「強弱強弱」ではこのメロディーは歌えないし,何よりメロディーが途切れ途切れになり,意味をなさなくなる。
同様の例として,ショパンの「バラード第3番」の第2主題もそうだ。これは6/8拍子の曲だが,この第2主題のフレーズはすべて6拍目から始まって次の小節の1拍目に終わる。というか,この楽節は全て3拍目,6拍目にアクセントがあり,「強・弱・弱・強・弱・弱」ではない。
このブラームスやショパンのようなメロディーは,専門用語では「アウフタクト」と呼ばれていることは,音楽好きの方ならご存知と思う。アウフタクトの伝統的日本語訳は「弱起」,すなわち「弱い拍から始まる」であるが,もしかしたら「アウフタクト=弱拍」とした事自体が間違いではないだろうかと思ったりする。
「アウフタクト」とは本来,「上昇する拍」という意味であって「弱い拍」という意味合いは持っていない。「アウフ」とは指揮者の腕の振りの方向,あるいはヴァイオリンのボウイングの腕の方向の意味ではなかったろうか。要するに,アウフタクトとは本来「指揮者が腕を上に振り上げる時に始まるメロディー」の意味で,「弱拍から始まるメロディー」の意味はなかったはずだ。
そうなると,本書にあるとおりベートーヴェンの「運命」主題の意味も分かる。もちろん,八分休符の後に3つのト音が続くあの有名な主題だ。これを,「1拍目は強拍であるはず」と考えると,あの強烈なテーマが弱拍から始まることになり,訳が分からなくなるが,これを「指揮者が腕を振り上げて始まるテーマ」であり,「弱・強・弱・強」のアフタービートの弱拍の1拍目が休みで強音から始まるテーマと考えると,極めて自然に解釈できるのだ。
「フィン・ウゴル語族系の言語を母語としている作曲家,たとえばバルトークにはアフタービートでない作品が多い」という本書の指摘も興味深い。私は以前,バルトークのピアノ曲ばかり弾いていた時期があるが,確かに彼の曲にはアフタービートはほとんどなかった。
このような観点からブラームスやリストの「ハンガリー舞曲/狂詩曲」を見直してみるのも面白い。ブラームスのハンガリー舞曲のほとんどの曲はアフタービートがないし,リストのハンガリー狂詩曲の前半(ラッサンと呼ばれる部分)もアフタービートはない。ハンガリー狂詩曲の場合,後半の速い部分(フリスカ)になると突然アフタービートが登場することがある。これなどは,「ズンチャ,ズンチャのリズムじゃ単調で飽きちゃうよ。アフタービートでなきゃ,ノリノリにならないぜ!」という感じじゃないかと思う。
ブラームスやリストの同時代人たちはハンガリー舞曲やハンガリー狂詩曲を聴いて,「俺たちのリズムの刻み方と全然違ってるけど,こんなリズムもあり?」なんて言いながら聞いていたのだろうか(下記譜例はモシュコフスキ編曲のブラームス「ハンガリー舞曲」第1番,第5番冒頭)。
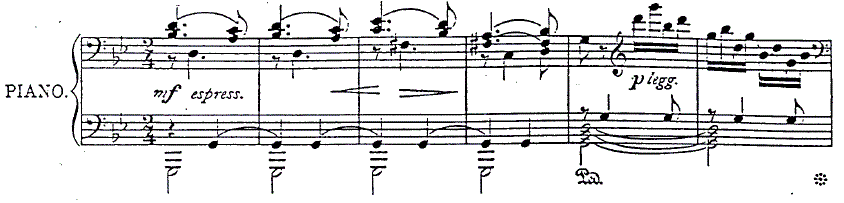
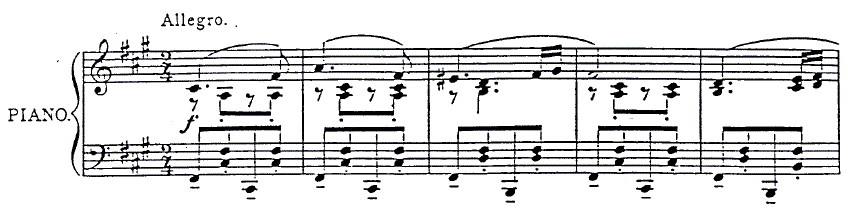
同様のことは,第2章で取り上げている「モーツァルトの装飾音」も目からウロコだった。モーツァルトは「装飾音を弾いて欲しくて装飾音を書いた」のではなく,「装飾音を勝手に弾いて欲しくなくて装飾音を書き入れた」のだ。これは「17世紀のヨーロッパ音楽の演奏の常識」を知らないと理解できないことだ。
「楽譜の通りに弾け」と教えられた人間にとっては信じられないことだが,実はヨーロッパ音楽では「楽譜通りに演奏しなければいけない」なんて常識はなかったことは,音楽史を勉強するとすぐに分かると思う。音楽とは自由に装飾音を即興で加えながら演奏するもの,というのが作曲当時の常識だったのだ(もちろん,どのように装飾を加えて演奏していたかはタイムマシンにでも乗らなければわからないわけだが・・・)。
要するに,「ベートーヴェンのアクセント」も「モーツァルトの装飾音」も「当時の暗黙の了解」であり,「その時代の人間なら誰でも知っている」ことだ。だから,それが作られた時代には誰でも意味が分かっているが,時代が変わってしまうと誰もその意味が分からなくなってしまう。
また,調性を否定する現代音楽から逆算して「調性音楽とはいったい何なのか」を探る考察もスリリングだ。
1970年代初めの現代音楽の全盛期を,私はリアルタイムで経験している。FMでは毎週何回も現代音楽祭が放送され,新作が演奏されていたと記憶している。演奏されるのはガチガチの12音音楽ばかりで,中には,楽譜を舞台にぶちまけてバラバラにし,それを拾い上げた順序に演奏する,なんて曲もあった。拾い上げた楽譜の上下が逆でもそのまま演奏する曲もあり,それらは偶然性音楽と呼ばれていた。
だが,熱にうなされたような現代音楽の熱気はいつの間にか消え去ってしまった。すると,憑き物が落ちたように現代音楽がつまらなくなった。「王様は裸だ」と誰かが言わない限り,王様は裸に見えないものなのだろう。今考えると,あれは「現代音楽バブル」だったと思う。
(2012/01/17)